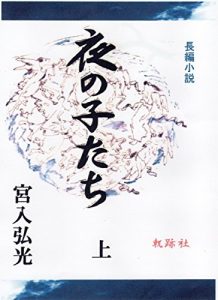kindleの電子書籍の第一冊を出してから、丸一年、85歳の私は「宮入弘光の文学の軌跡」を除いて、11冊目となる。……創作は一編も書いていない。「役者という存在・宮口精二」のあとがきに「あとどのくらい生きられるか、自然は黙教えてくれないが、〔長編小説 少年の渚〕を書こうと考えている。……この愚かさはどうしょうもない。」と書いた時間が、消えずに続いている。
なぜ、作品の紹介文をこのようなことから書き始めたかというと、まず、私の気性として宣伝文が苦手であり、書くのが好きでない理由がまずある。……しかしそんなことより、今の自分が過去の時間の世界へとぼとぼ歩いて、まるでのろい速度で飛んでいる流れ星のような感覚の中にいること、……と同時に、過去の私がやはりのろのろもう一本の流れ星になって、その二本の流線が交差していて、何とも言葉が見つからないという状態にいるからだ。おそらくこの文章を書いている私は、その意識はその交差した唯中にいるからであろう。――そこで、いきなり半世紀以上前の自分を見てみよう。
……「私祭」を半世紀以上、読み返していなかった作者である私に、――昨年、八十四歳になって書き上げた、長編小説[夜の子たち]の発想の素が、これほどまでに「私祭」に根を張っているとは、思っていなかった、その驚きだ。
[夜の子たち]の世界は、穏やかな水面下沈み込んでいるが、母の遺骨の海への散骨、母と息子とある夫婦から×印に交差して、自殺が起こる。に人間関係の絡み方は、在り方は同質だか、不思議に人間の葛藤があっても穏やかだ。どうしてそのような世界が生まれて来たのか。……私、作者の眼にはその疑問を己の中に抱きながら、二本の異質な流れ星の交差の中に見えてくる。
この作品を書いた昭和三十四年の時代においては、風葬という言葉は昔からあったが、法的に散骨という風習はまだなく、認められてもいなかった。いまの若い人たちには、広く認められているのにと思うかもしれないが、作家の平林たい子が作者に向かって、――法的に認められていませんね]と一言話されたことがあった。
ところで、今の私は、ため息をつくように自分で呟いている。
この昨品の初校は「風葬」と題して、百枚の作品として書いていた。しかしどうしても自分で納得できず、一年半かけて書き直した。題も「私祭」に変えた。
自分で納得できなかった理由は、なぜ、息子は自殺した母の遺骨を海へまかなければならなかったのか。いや、その前に、今では考えられない擂鉢で遺骨を粉に気でしなければならなかったのか。一番重要なその問題が、曖昧だったからである。……題名は忘れたが子供のとき聞かされた、客が来ると夜中に刃物を砥ぐおじいさんおばあさんの怖いおとぎ話を思い出して、背筋が寒くなる今の私。
それはともかく、主人公の息子に散骨を行く必然性をようにどうしたら形に表せるか、考えに考えてみて行ったら、このような不倫、しかも母子とある一組の夫婦が×印となって、劇的に展開させなければならなかった。
おそらく「私祭」とは何をさしているのか、と疑問、不審を抱く人もいるだろう。それは――いかような意味においても、自分自身を祭る行為た。……実は、人間はこの世に誕生して来て以来、それを行ってきて生存している、人間の死は自分の死だということを実感できないからで、親しい人の死の悲しみは、己の死の悲しみそのものだと気付くことができない、それだけのことだ。
われわれは日常生活の中で、自然に悲しみが癒される……。それでいいのだ。生活していく力には、「悲しみ」は必要だがその中から生まれてくる力、粗利が人間が備えている生命力だから……。
……「私祭」の主人公の正也にとって、母の恒子は自分であったら?」
と言ったら、怪訝な顔をするだろう。母の自殺という辛く悲しい、憤りをモ覚える自殺そのものから超えるために、母の遺骨を擂鉢で粉にして、海に撒く……、正也が突き詰めて達したところは、己を同時に祭ることであった。
日本の近代文学には「神話」という「悲劇」の基盤が失われている。逆に言えば、悲劇を生むための神話の創造が、今の文学に不可欠だ、しかし、そのことに気づいている作家は、果たしているのだろうか。
未完成な部分が多く見られながら、仏文学者の長尾喜又、児童文学作家の吉田タキノ、などの方々から劇的な小説と認められた。そして、旧友の、文芸評論家・石井冨士弥、「軌跡」の同人だった泉茂久から、それなりに評価された。
しかし、この作品を「軌跡」の二人の仲間から、――不潔だ! 詰まらない」の一言で切り捨てられたことが原因で、自分が作った『軌跡』を去る事件が起きた。そのことは、ほかで書いたので、立ち入らない、石井冨士弥と、「軌跡」の同人泉茂久が寄せてくれた読後感は「あとがき」に載せておいた。
さて、過去から近づいてくる私、……「私祭」を書いた作者は、「敬虔な怒り」とい長編小説へ向かって暗中模索しながら歩んでいく。そこも不倫、自殺、殺人の世界だ。
しかし、殺人の果てに、その登場人物の怒りを敬虔な行為へ消化させる世界を展開していく。
それから二十二年の歳月を経て、千三百五十枚の[夜の子たち]を書き上げた。
劇的な世界を描きながら、自殺、不倫、散骨を扱いながら、「私祭」とはなんと違って、静かな緊迫した世界なのか、と一人話す相手もなく呟いている。
「逆光」について。
何とも奇妙な、得体のしれない、戦争で夫を失った未亡人が、疎開していた時であった少年、いま青年となった渥見と出遭ったことから、……一緒に生活していた青年殺していく、世界が展開していく。
――君の小説を読むと死の世界へつれて行かれそうだよ」とかって「日通文学」の編集長だった田代儀三郎が直接作者に語ったことがある。彼の五十歳頃だ。
いやはや、なんといっていいのか言葉が亡くなってきた。いま書こうとしている「少年の渚」は、恐らく問上の女性のために、自分の命をささげて悔いない少年の悲劇になるだろう。……書けたら、それまでこの世にいられたらの話である。
sisai giyakoo (siyosetusyu) (Japanese Edition)
Sobre
Baixar eBook Link atualizado em 2017Talvez você seja redirecionado para outro site