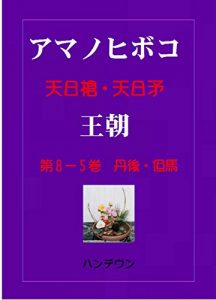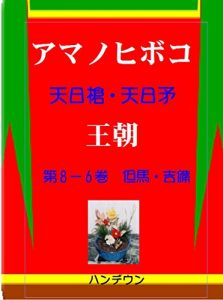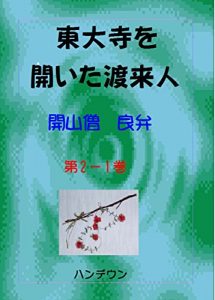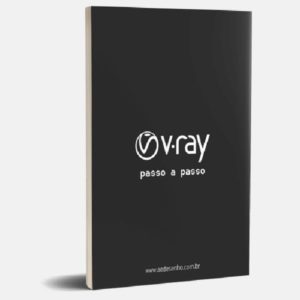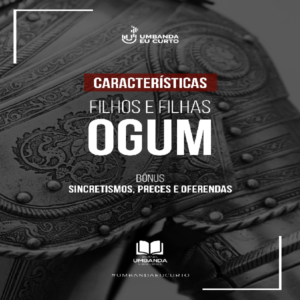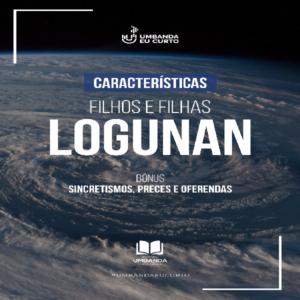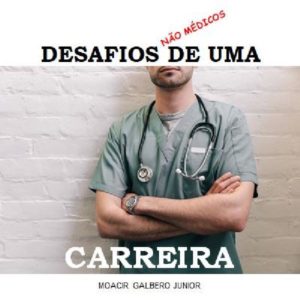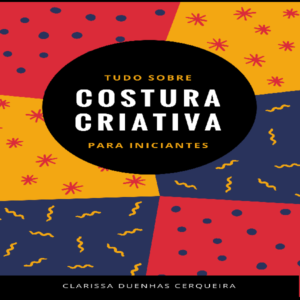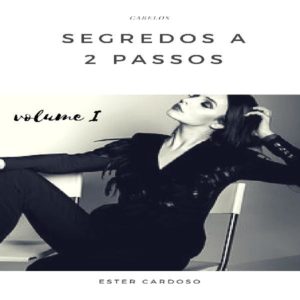アマノヒボコ王朝 5 丹後・但馬
★大和百済王朝以前にアマノヒボコ(天日槍・天日矛)新羅王朝が存在した。倭国には、遠い昔から強固な朝廷が存在していたという〝幻の大和朝廷〟論に欺かれてはならない。
〔本書の基本史観〕
◎自分探しの旅は、先祖探しの旅になり、歴史への旅となった。その途上、日本古代史の数々の偽造に気づいた。どうして、そうなるのか。その疑問を解き明かす熱情の旅になった。
◎日本列島は紀元前後、14、5世紀のアメリカ大陸や17、8世紀のオーストラリア大陸のように原住民(縄文人)しか住まない新天地だった。その新天地を、韓半島からの渡来人(弥生人)が開拓していった。
◎しかし、そうした渡来人の活躍は闇に葬られてきた。先祖を隠蔽したそのような歴史は砂上の楼閣に過ぎず、先祖を元のあるべき姿へ復元しなければならない。それが、現代に生きる子孫の果たすべき役割と信じる。
〔序言〕
自分は何者なのか。在日韓国人として、なぜ日本で生まれなければならなかったのか。その青春の疑問から、いつしか歴史の旅が始まった。『日本書紀』に目を通したとき、実に訳のわからない書だったが、韓(朝鮮)半島関係の記述が多く、〝朝鮮書紀〟じゃないかと思ったくらいだ。縄文人しか住んでいなかった当時の日本列島は、14、5世紀のアメリカ大陸や17、8世紀のオーストラリア大陸のように原住民しかすまない新天地でり、韓半島からの渡来人(弥生人)は日本列島に定住、開拓していったのだ。
そうした痕跡を探し求めるため、実に多くの書を読破した。しかし、韓(朝鮮)半島との親密な関係を論述する書はほとんどなく、多くは日本が韓(朝鮮)半島支配していたという倒錯の論考である。歴史は人間の営みであって、神業の賜物ではない。新井白石は「神は人なり」と喝破したように、神業の史実を作り出してはなるまい。が、本居宣長など多くの研究者は、韓半島との関係に論述せず、神業の史実を多用した。〝存して論ぜず〟は、神業の史実を論じるなという教えであり、それがため、多くの人が歴史を正視せずして、とんでもないことを正当化している。罪深きことである。
自分自身の淵源を訪ねる歴史旅の途上、『日本書紀』自体が偽造の書であることを知り、その『日本書紀』の記述を正当化せんがための論考が拡大生産されて、日本はまさに、韓半島との関係を断ち切った〝歴史偽造大国〟になっている。それは、先祖に対する冒涜であり、神に対する冒涜でもある。日本人自身がそうした偽造を正していかなければならないにもかかわらず、経済的利益を優先するあまり、歴史偽造を拡大再生産して、韓国併合という罪業まで敢行した。真の歴史を探求していくことこそが韓日親善を定立する礎であると信じる。
奇しくも日本に生まれた在日韓国人として、韓半島にルーツを持つ者として、闇に葬られた先祖の事績を正しく検証し、復元したいという熱情にかられた。それは、自分が何者かという青春の疑問に対して、回答を求める旅であり、遠く古代にまでつながるであろう自分探しの旅であり、先祖に感謝する旅でもある。自分が何者かを知りたいと思ったら、本書を熟読していただきたい。その前に『日本書紀』を通読されることをお勧めする。
目次
〔74〕 籠(この)神社 京都府宮津市字大垣430
〔75〕 真名井(まない)神社(籠神社奥宮) 京都府宮津市中野
〔76〕 豊受大(とようけだい)神社 京都府福知山市大江町天田60
〔77〕 皇大(こうたい)神社 京都府福知山市大江町内宮217
〔77〕 皇大(こうたい)神社 京都府福知山市大江町内宮217
〔78〕 天岩戸(あまのいわと)神社 京都府福知山市大江町佛性寺日浦ヶ嶽206-1
〔79〕 溝谷(みぞたに)神社 京都府京丹後市弥栄町溝谷46-2
〔80〕 四所(ししょ)神社 兵庫県豊岡市城崎町湯島447
〔81〕 楽々浦(ささうら) 兵庫県豊岡市城崎町楽々浦
〔82〕 韓国(からくに)神社 兵庫県豊岡市城崎町飯谷字落シガ谷
〔83〕 気比(けひ)神社 兵庫県豊岡市気比字宮代286
〔84〕 伊伎佐(いきさ)神社 兵庫県美方郡香美町香住区余部字宮内2746-2
〔85〕 中嶋(なかじま)神社 兵庫県豊岡市三宅1
〔86〕 大生部兵主(おおいくべひょうず)神社 兵庫県豊岡市奥野1
〔87〕 葦田(あしだ)神社 兵庫県豊岡市中郷森下1141
〔88〕 出石(いずし)神社 兵庫県豊岡市出石町宮内99
〔89〕 伊豆志坐(いずしいます)神社 出石神社旧称
〔90〕 諸杉(もろすぎ)神社 兵庫県豊岡市出石町内町28
あとがき
まえがき
丹後には、『日本書紀』にも浦島伝説があり、また羽衣伝説がある。さらに間人(はしひと)皇后が丹後に一時避難したことから、間人(たいざ)という地名が生じたという故事もある。アマノヒボコが但馬の地に定住したしたいうが、その地に隣接するのが丹後であり、但馬と同一地といってもよい。原初は丹波と称された地であり、四道将軍の一人、丹波道主が派遣された地である。にもかかわらず、古代史の上でははなはだ軽視されている。
古代の丹波国は、713年(和銅6)に分離し、丹波後国、丹後国となったが、大和国より古く、出雲に匹敵する王国であったという。ヒボコ定住の地、但馬の探索を前に、その丹後を訪ねることにした。籠神社81代目宮司の海部穀定(よしさだ)氏が著した『元初の最高神と大和朝廷の元始』(桜楓社)という書は、そのよき羅針盤である。
朝倉治彦ほか編の『神話伝説辞典』には「新羅の王子とされる天之日矛を始祖とし、但馬、播磨、淡路(いずれも兵庫県)、近江(滋賀県)、若狭(福井県)、摂津(大阪府)、筑前(福岡県)、豊前(大分県)、肥前(長崎県)等にわたり、広大な分布を持っていた大陸系の種族。記紀や風土記には、天之日矛ないしその妻の女神(アカルヒメ)の巡歴伝説ないし鎮座伝説として語られる。この族人に田道間守、清彦、神功皇后の母君などがある」とある。まさに、ヒボコとその子孫は但馬のみならず播磨、摂津、大和、近江等、遠くは九州まで住居して活躍していたことになる」とある。
ここでも、丹後が抜けているが、これだけ広範に活躍できたということは、その当時、ヒボコに敵対する勢力がほとんどいなかったということであり、換言すれば、倭地は、ヒボコの時代、未開の荒蕪の地であったということにほかなかろう。ヒボコ一族は、縦横無尽に活躍し、闘いといえば、播磨での伊和大神(大己貴命)、つまり先住の出雲族との闘いであるが、その闘いも牧歌的な〝国占め〟の争闘であって、血を血で洗うという凄惨な闘いの雰囲気はない。
丹後では、何だかの争闘があったのだろうか。
〔74〕 籠(この)神社 京都府宮津市字大垣430
金達寿さんは、『日鮮同祖論』で有名な金沢庄三郎の考証を紹介する。
「余社は倭名抄丹後ノ国与謝ノ郡の地で、雄略天皇22年紀には丹波ノ国余社ノ郡とある。丹波国の五郡を割いて始めて丹後国を置いたのは和銅6年で、それより以前は丹波国であった。丹後ノ国与謝ノ郡の天梯立は伊射奈芸ノ命が天に通わんために作り立てたまいしものの仆(たお)れたので、その東ノ海を与謝、西ノ海を阿蘇というと、風土記に見え、又、天照大神を但波吉佐宮に4年間斎き奉ったこともあり(倭姫世紀)、往古は由ある土地と見えて、ヨサ、アソの名はまた民族ソと通ずるところがある。以上、阿蘇・伊蘇・伊勢・宇佐・余社などはいずれも我民族移動史の上に重要なる地位を占めている土地であって、しかも民族名ソ及び其類語を名としていることは、最も注目に価する事実といわねばならぬ」
以上であるが、古代の丹波国は、大和国より古く、丹後、丹波、若狭、但馬を含む大国であり、出雲に匹敵する王国であったという。713年(和銅6)に分離し、丹波後国、丹後国となった。
盛夏のある日、福知山駅から車を飛ばして、酒呑(しゅてん)童子という鬼伝説のある大江山を越えて、元伊勢といわれる籠神社に参拝した。まさに天の橋立の一方の根っこの部分にあって、土産店などが軒を並べる観光地の中心にあり、大型観光バスが何台も駐車していた。
籠神社の由緒書に、「古称吉佐宮、御祭神 彦火明命、相殿 豊受大神 天照大神 海神 天水分神」とあって、「神代の昔より奥宮眞名井原に豊受大神をお祀りして来ましたが、その御縁故によって崇神天皇の御代に天照皇大神が大和国笠縫邑からおうつりになって、之を吉佐宮と申し、豊受大神と共に4年間お祀り致しました。その後天照大神は垂仁天皇の御代に、又豊受大神は雄略天皇の御代にそれぞれ伊勢におうつりになりました。それに依って当社は元伊勢と云われております。両大神がおうつりの後、天孫彦火明命を主祭神とし、社名を籠宮と改め、元伊勢の社、又丹後国一之宮として朝野の崇敬を集めてきました」と記されている。
「伊勢へ詣らば 元伊勢詣れ 元伊勢 伊勢の故郷じゃ 伊勢の神風海山越えて 天橋立吹き渡る」という俗謡があり、伊勢神宮の故郷であることを歌っている。とするならば、籠神社を奉斎したのはヒボコ一族ともいわれているから、出石族の自己主張ということだろうか。
Amanohiboko Ouchou 5 (Japanese Edition)
Sobre
Baixar eBook Link atualizado em 2017Talvez você seja redirecionado para outro site