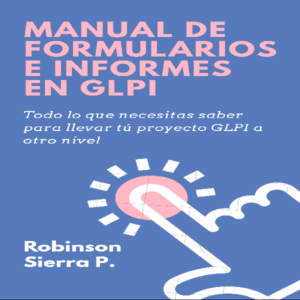通りを行く、なんでもない日常を生きる人々の目線、その背景に広がる世界遺産に認定された古い街並み、熱気、息づかい。
2015年のキューバ・ハバナの街や人々を切り取った写真。
It is just before sunset. I find shelter from a sudden downpour under the eave of a building.
Standing there, I hear music coming from somewhere further inside the adjacent apartment.
Drawn towards the sound, I turn my ear towards the half-closed, dimly lit shutters when an old man calls out to me from within.
“My grandson is in the garage practicing with his band. You want to take a look?”
“I’d like to see that! I’d like to hear that!” I reply, and the man guides me inside.
I was drawn to Cuba through my love of Latin music and because I was fascinated by a country that had not been touched by capitalism,
in spite of its proximity to the United States.
Reaching the garage, I find a huge band comprised of ten young people. They were playing Latin rhythms with a dose of hip hop
– not the sort of sound you would find emerging from Japan.
“I actually like Eminem best,” the band leader tells me in broken English. “I love Japanese manga!”
Here I was, in a socialist country that took me a whole day to reach from Japan – these words took me back somewhat.
Once relations are back on track with the US, the nostalgic reminders of a time past in this nation will give way to the mundane scenery
we are all familiar with. But this kind of selfish thought – wanting things to stay as they are – held by mere travelers such as myself may
be at complete odds with the sentiments of those who live in this city.
日没少し前、急なスコールをビルの軒先でやり過ごしていたら、隣のアパートの奥から音楽が聞こえてきた。
その音の響きにつられ、半分閉まった薄暗いシャッターの前で耳をそばだてていると、おじいさんに呼び止められた。
「孫のバンドがガレージで練習中なんだよ。見ていく?」
僕はもちろん「見たい! 聴きたい!」と答え、中へと案内された。
キューバにやってきたのは、ラテン音楽が好きだったのと、アメリカと至近距離にありながら資本主義的文化が全くないという国に興味があったからだ。
練習していたのは、10人編成で大所帯の若いバンド。音は、伝統的なサルサにHIPHOPを足したような、日本では生まれえないようなものだった。
バンドリーダーと片言の英語で話をしてみると、「本当はエミネムが一番好きなんだ」「日本のマンガ・アニメ大好き」と、
日本から丸1日かけてたどりついた社会主義国で聞くには、意外な言葉ばかりだった。
アメリカとの国交が回復したら、もう地球上のほかの国では決してみられない20世紀の国家のノスタルジーがそのまま残るこの国が、世界中でありふれた風景へと変わってしまう。
なんて僕ら一介の旅行者は、勝手なことを思うけれど、現地で生きる人たちの心情は僕たちには知る由もない。
2015年のキューバ・ハバナの街や人々を切り取った写真。
It is just before sunset. I find shelter from a sudden downpour under the eave of a building.
Standing there, I hear music coming from somewhere further inside the adjacent apartment.
Drawn towards the sound, I turn my ear towards the half-closed, dimly lit shutters when an old man calls out to me from within.
“My grandson is in the garage practicing with his band. You want to take a look?”
“I’d like to see that! I’d like to hear that!” I reply, and the man guides me inside.
I was drawn to Cuba through my love of Latin music and because I was fascinated by a country that had not been touched by capitalism,
in spite of its proximity to the United States.
Reaching the garage, I find a huge band comprised of ten young people. They were playing Latin rhythms with a dose of hip hop
– not the sort of sound you would find emerging from Japan.
“I actually like Eminem best,” the band leader tells me in broken English. “I love Japanese manga!”
Here I was, in a socialist country that took me a whole day to reach from Japan – these words took me back somewhat.
Once relations are back on track with the US, the nostalgic reminders of a time past in this nation will give way to the mundane scenery
we are all familiar with. But this kind of selfish thought – wanting things to stay as they are – held by mere travelers such as myself may
be at complete odds with the sentiments of those who live in this city.
日没少し前、急なスコールをビルの軒先でやり過ごしていたら、隣のアパートの奥から音楽が聞こえてきた。
その音の響きにつられ、半分閉まった薄暗いシャッターの前で耳をそばだてていると、おじいさんに呼び止められた。
「孫のバンドがガレージで練習中なんだよ。見ていく?」
僕はもちろん「見たい! 聴きたい!」と答え、中へと案内された。
キューバにやってきたのは、ラテン音楽が好きだったのと、アメリカと至近距離にありながら資本主義的文化が全くないという国に興味があったからだ。
練習していたのは、10人編成で大所帯の若いバンド。音は、伝統的なサルサにHIPHOPを足したような、日本では生まれえないようなものだった。
バンドリーダーと片言の英語で話をしてみると、「本当はエミネムが一番好きなんだ」「日本のマンガ・アニメ大好き」と、
日本から丸1日かけてたどりついた社会主義国で聞くには、意外な言葉ばかりだった。
アメリカとの国交が回復したら、もう地球上のほかの国では決してみられない20世紀の国家のノスタルジーがそのまま残るこの国が、世界中でありふれた風景へと変わってしまう。
なんて僕ら一介の旅行者は、勝手なことを思うけれど、現地で生きる人たちの心情は僕たちには知る由もない。