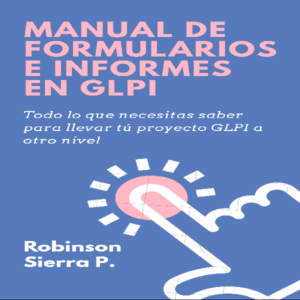ここは魔法国家。学歴よりも容姿よりも家よりも、今まで何かをしたかですらない。
――この国では、魔力ですべてが決まる。
生まれたときに測定される魔力の量。
それこそが、すべての人生の価値を決めてしまう。
なぜなら、その魔力によって社会が動いているからだった。
電車もコンビニもスマホですら、国民から供給される魔力で動かされている。
魔力会社にどれだけの魔力を安定供給しているか、それこそが社会に対する貢献度を決める。
その貢献度に応じて社会の評価が決まり、対価すら支払われる。
ゆえに魔力がありさえすれば、生まれながらに富豪となる。
しかし。
――俺には、魔力が無かった。
主人公のアルは、魔力G評価。
魔力無しは社会の最底辺の存在だった。
公務員になることはできず、国民健康保険にすら登録することができない。
――何かが間違っている。何かが。
生まれたときに一瞬測られるその力こそが、すべてを決めてしまう。
鍛えたら魔力が増えることはない。
――魔法で、いじめられるということ。
アルは凍らされたり、小さな炎をぶつけられたり、果ては学校の校門前を地割れによって封鎖される。
その結果、遅刻することになったりする。
魔力無しは、いじめられても仕方がない社会だった。
――間違ってる!
こんなこと、すべて間違ってるとアルは心底思う。
しかし、抗うことができなかった。
自殺しようと屋上から飛び降りようとしていると、奇妙なほど真っ黒な指輪を見つける。
その指輪を拾うと、和服を着た少女が突然現れる。
「おうおう、指輪をこんなところに落としてしまったか」
「誰だ」
「わしか? 竜だよ竜」
滅んだはずの竜だった。
魔法使いの驚異であった竜は数百年前に滅んだはずだった。
今の魔法国家の急速な発展も、竜の存在が消えたからこそ実現したもの。
なぜなら。
竜は、魔法使いの魔力を喰らうことができる……!
一度、食われてしまった魔力は戻ることがない。
魔法使いが魔法を使うときに名乗る「真名」さえ知ることができれば、
竜は魔力を喰らうことができると言った。
なぜ、滅んだはずの竜がこんなところにいるのか。
「第一、二百年前に竜は滅んだんじゃなかったのか?」
「竜が滅んだ? 人間はおかしなことを言うな」
竜を名乗る少女は誇らしげに言った。
「竜は別の進化を遂げたのだよ。人間にわかりやすく例えるなら、三次元から四次元の存在へとだな。そうなれば人間に竜が見えなくなるのも当然ではないか」
「俺はお前が見える」
「それはおぬしがその指輪に触れているからだぞ」
奇妙なほど真っ黒な指輪は、竜交の指輪だという。
それこそが、見えなくなったはずの竜を見ることができる指輪だった。
アルは確信した。
――この国を変えられる!
すべての魔法使いの真名を調べ上げて、その魔力を喰らうことができれば……
この歪んだ魔法国家を打倒することができる。
竜は久しぶりに人間の魔力を食いたいと言う。
アルは人間でありながら、竜に魔力をいくらでも食わしてやると言う。
「おぬしは、わしと契約するのだな? 死をいとわぬ覚悟があるのだな?」
「契約する!」
「おぬしは竜使いになったのだ」
竜使いの国家反逆計画、始動!
すべての間違った常識を覆すために、少年が竜と共に立ち上がる。
まずは自分をいじめていた人間の魔力を喰らうことになるが……それこそが引き金となる。
見えない竜を使えば、完全犯罪は可能だった。
まして滅んだと考えられている竜の仕業だと誰が考えられるのか。
警察ですら犯人を特定することができず、黒魔術師の犯行と断定し、捜査はアルの優位に進むかと思われたとき。
「竜使いがいるかもしれないと言いたいだけですよ」
ハヤセ・ベルモット登場。
七大魔術師と呼ばれるこの国の魔力事情の50パーセント近くをたった七人で担う一人。
白い探偵と呼ばれ、数々の難事件を解決してきた名探偵だった。
ハヤセは、的確な手法で最初の被害者をあっけなく特定してしまう。
「さぁ、ここからが本題です」
少年は竜を使ってこの社会の閉塞感を打破できるのか?
名探偵こそが竜使いを特定し、この社会を守るのか?
国家をかけた「心理戦」が始まる。
完全ファンタジー×心理戦という異色の組み合わせで贈る実験作、ここに。
――この国では、魔力ですべてが決まる。
生まれたときに測定される魔力の量。
それこそが、すべての人生の価値を決めてしまう。
なぜなら、その魔力によって社会が動いているからだった。
電車もコンビニもスマホですら、国民から供給される魔力で動かされている。
魔力会社にどれだけの魔力を安定供給しているか、それこそが社会に対する貢献度を決める。
その貢献度に応じて社会の評価が決まり、対価すら支払われる。
ゆえに魔力がありさえすれば、生まれながらに富豪となる。
しかし。
――俺には、魔力が無かった。
主人公のアルは、魔力G評価。
魔力無しは社会の最底辺の存在だった。
公務員になることはできず、国民健康保険にすら登録することができない。
――何かが間違っている。何かが。
生まれたときに一瞬測られるその力こそが、すべてを決めてしまう。
鍛えたら魔力が増えることはない。
――魔法で、いじめられるということ。
アルは凍らされたり、小さな炎をぶつけられたり、果ては学校の校門前を地割れによって封鎖される。
その結果、遅刻することになったりする。
魔力無しは、いじめられても仕方がない社会だった。
――間違ってる!
こんなこと、すべて間違ってるとアルは心底思う。
しかし、抗うことができなかった。
自殺しようと屋上から飛び降りようとしていると、奇妙なほど真っ黒な指輪を見つける。
その指輪を拾うと、和服を着た少女が突然現れる。
「おうおう、指輪をこんなところに落としてしまったか」
「誰だ」
「わしか? 竜だよ竜」
滅んだはずの竜だった。
魔法使いの驚異であった竜は数百年前に滅んだはずだった。
今の魔法国家の急速な発展も、竜の存在が消えたからこそ実現したもの。
なぜなら。
竜は、魔法使いの魔力を喰らうことができる……!
一度、食われてしまった魔力は戻ることがない。
魔法使いが魔法を使うときに名乗る「真名」さえ知ることができれば、
竜は魔力を喰らうことができると言った。
なぜ、滅んだはずの竜がこんなところにいるのか。
「第一、二百年前に竜は滅んだんじゃなかったのか?」
「竜が滅んだ? 人間はおかしなことを言うな」
竜を名乗る少女は誇らしげに言った。
「竜は別の進化を遂げたのだよ。人間にわかりやすく例えるなら、三次元から四次元の存在へとだな。そうなれば人間に竜が見えなくなるのも当然ではないか」
「俺はお前が見える」
「それはおぬしがその指輪に触れているからだぞ」
奇妙なほど真っ黒な指輪は、竜交の指輪だという。
それこそが、見えなくなったはずの竜を見ることができる指輪だった。
アルは確信した。
――この国を変えられる!
すべての魔法使いの真名を調べ上げて、その魔力を喰らうことができれば……
この歪んだ魔法国家を打倒することができる。
竜は久しぶりに人間の魔力を食いたいと言う。
アルは人間でありながら、竜に魔力をいくらでも食わしてやると言う。
「おぬしは、わしと契約するのだな? 死をいとわぬ覚悟があるのだな?」
「契約する!」
「おぬしは竜使いになったのだ」
竜使いの国家反逆計画、始動!
すべての間違った常識を覆すために、少年が竜と共に立ち上がる。
まずは自分をいじめていた人間の魔力を喰らうことになるが……それこそが引き金となる。
見えない竜を使えば、完全犯罪は可能だった。
まして滅んだと考えられている竜の仕業だと誰が考えられるのか。
警察ですら犯人を特定することができず、黒魔術師の犯行と断定し、捜査はアルの優位に進むかと思われたとき。
「竜使いがいるかもしれないと言いたいだけですよ」
ハヤセ・ベルモット登場。
七大魔術師と呼ばれるこの国の魔力事情の50パーセント近くをたった七人で担う一人。
白い探偵と呼ばれ、数々の難事件を解決してきた名探偵だった。
ハヤセは、的確な手法で最初の被害者をあっけなく特定してしまう。
「さぁ、ここからが本題です」
少年は竜を使ってこの社会の閉塞感を打破できるのか?
名探偵こそが竜使いを特定し、この社会を守るのか?
国家をかけた「心理戦」が始まる。
完全ファンタジー×心理戦という異色の組み合わせで贈る実験作、ここに。