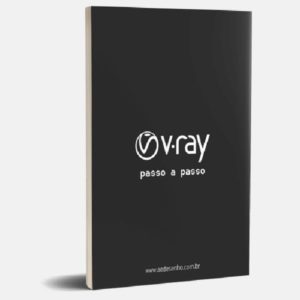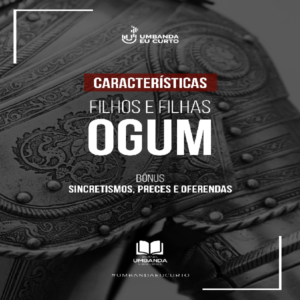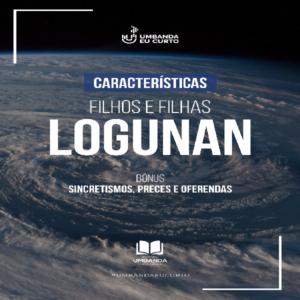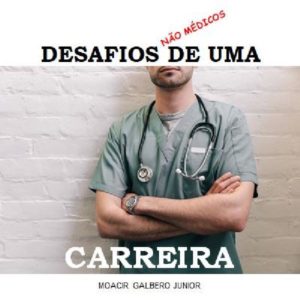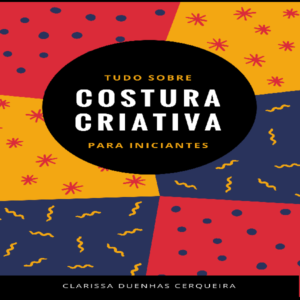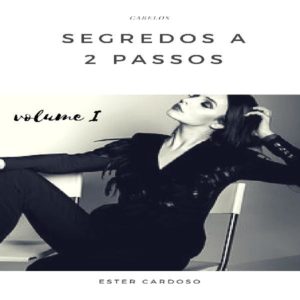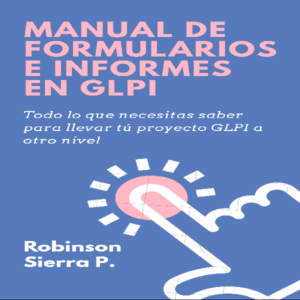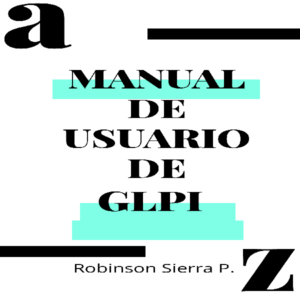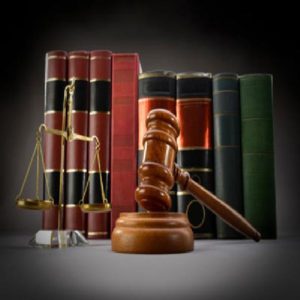はじめに
2003年に『ロシアの軍需産業』、2009年に『「軍事大国」ロシアの虚実』をともに岩波書店から上梓したことがある。その後、『ロシアの最新国防分析(2013年版)』をKindle版として刊行した。定期的な内容刷新を予定していたが、このたび、ようやく実現の運びとなった。
本書の目的は、ロシアの国防状況を世界全体の変化のなかで位置づけ、その現状を提示すると同時に、その問題点を明らかにすることにある。そのためには、ロシアの「現実」をできるだけ詳細に知り、それらを緻密に分析しなければならない。この姿勢を守りながら、その背後にある「制度」にまで踏み込んだ考察をするように心がけたつもりである。おそらく本書以上に詳細にロシアの軍事関連問題を考察した類書は、日本はもちろん、欧米にもないだろうと自負している(1)。
本書は2016年11月に上梓した拙著『ガスプロムの政治経済学(2016年版)』と対になっている。同書を読めば、ガスプロムという個別の企業からみたロシアの現状が理解できるようになるだろう。その意味で、この本を読んだうえで、『ロシアの最新国防分析(2016年版)』を読めば、より深くロシアの現状を考察することができるようになるはずだ。
もっとも大切なのは、ロシアをどういう視角から理解しようとするかである。タイトル上、国防関連が分析対象となるが、国防だけを考察しても決してロシアの内実を探ることはできない。したがって、国防も政治も、経済もそれなりの知見がなければならない。加えて、ロシアの歴史的な変遷についても一定の理解を要する。たとえば、筆者は『ロシア革命100年の教訓』という本を刊行予定だが、こうした基本的知識が国防分析に新しい視角をもたらしてくれるものと信じている。
それだけでは足りない。いわゆる「グローバリゼーション」のもとでは、世界の潮流の変化に敏感でなければならない。筆者は拙著『官僚の世界史:腐敗の構造』のなかで、「腐敗」、「官僚」、「正義」、「権力」といった問題を世界の歴史にわたって考察したことがある。こうした相対化がなければ、ロシアの国防状況は理解できないだろう。
こんな筆者が国防分析をするうえでもっとも大切だと思う視角は、ロシアにおける軍産複合体の重要性である。ロシア軍やロシア製軍備ばかりに目を取られていると、ロシア連邦という国家全体の実情を見失うことになりかねない。
米国の場合、ドワイト・アイゼンハワー元大統領が「軍産複合体」を産官学などの利害で結びついた巨大集団とみなしたことは有名だ。1961年の最後の退任演説において、350万人もの人々が直接、軍事エスタブリッシュメントにかかわり、全米企業の純所得よりも多い軍事安全保障費を毎年費やしている現状に警鐘を鳴らしたのである。すなわち、「軍事エスタブリシュメントと大規模な武器産業の結合」としての軍産複合体(military-industrial complex)の存在を警告した。アイゼンハワーは政府、軍、産業が不要な軍事力の拡大、過剰な国防支出、さらに政策作成過程におけるチェック・エンド・バランスの崩壊につながりかねないことを恐れていた。彼はつぎのように予言した。「軍産複合体による是認されていない影響力の獲得を、それが求められていようともいないとも、我々は見張らなければならない。見当違いの権力の破滅につながりかねない隆盛という潜在力が存在しているのであり、尾を引くことになるだろう」と。
ただし、本書でいうロシアの軍産複合体はもっとずっと狭義なイメージで語っている。軍備などの軍事品を開発・生産する企業体のようなものだ。こうした狭い軍産複合体であっても、ロシアではきわめて重要な役割を果たしており、国内政治に与える影響力も大きい。だからこそ、本書は軍産複合体に重大な関心を寄せている。わかりやすく言えば、それほど重大であるからこそ、ロシアには軍産複合体担当の副首相までいるわけだ。ドミトリー・ロゴジンである。ロシア大統領は軍産複合体の有力者と年2回、会合を開催し、国防発注などの遂行状況や軍備増強の進捗状況を確認する。それほど軍産複合体の役割は重大なのだ。
念のために入っておくが、アイゼンハワーが想定した、広義の軍産複合体がロシアに存在しないわけではない。おそらくそれに近いものがある。だが、広義の軍産複合体については、別の本を書かなければ、その実情を説明しきれないだろう。ここではあくまで狭義の軍産複合体からロシアの軍事問題にスポットをあてたい。簡単に言えば、軍産複合体に代表される経済面からの国防分析に力を入れているというのが本書の最大の特徴ということになるだろう。もちろん、軍改革や最新の軍備についても紹介するが、それはロシア全体の理解のための枝葉にすぎない。
もう一つの重要な視角は情報安全保障の重視である。ウラジミル・プーチン大統領自身、情報安全保障をきわめて重視しているのだが、本書ではサイバー空間をめぐるロシアの現状分析についても比較的丹念に考察したつもりである。つまり、国際関係のような表面的な問題から国防問題を推論するのではなく、軍産複合体や情報産業から抉り出すのである。
念のためにロシアの特殊性にも十分に配慮する必要があることも指摘しておきたい。「チェーカー」と呼ばれる諜報機関による支配に関連した問題である、ロシアの権力構造を論じるとき、「チェーカー」の役割は重要であり、それは他国にはみられない特徴となっている。だからこそ、序章で連邦保安局(FSB)を中心とする権力構造の分析からはじめることにした。
序章では、軍事問題を語る前に、ロシアでなにが起きているかについて、簡単な概説を行う。軍は国家の合法的暴力装置の一つだが、FSBという軍以上に大きな政治的権力を握る機関がある。ゆえに、FSBを中心にいまのロシアの政治的状況について一定の理解を深めてもらうために序章で、軍事問題とは直接かかわらない権力状況に関する考察を行うことにしたのである。
第1章では、軍事費の問題を取り上げる。世界的な軍事費の動行を踏まえたうえで、ロシアの軍事費の推移を分析する。軍事費を構成する重要な要素である国防発注の推移やその問題点についても考察する。最新兵器についても紹介する。
第2章では、軍改革について取り上げたい。2008年8月に起きた、いわゆる「5日間戦争」後、2012年11月のセルジュコフ国防相解任までの間、ロシアで行われた軍改革の概要を分析する。さらに、セルジュコフ解任の背景や、ショイグ新国防相のもとでの軍改革についてもふれたい。徴兵制や契約兵制などについても詳しく考察する。
第3章では、武器輸出を探究する。武器輸出の実態はもちろん、対中武器輸出への警戒感の問題、民間航空機の輸出問題についても考察対象としている。武器輸出はロシアの軍需産業にとってきわめて重要であり、武器輸出問題に対する深い理解がなければ、ロシアの国防問題を論じることはできないと強調しておきたい。
第4章では、軍産複合体を俎上に載せる。ロシアの政治勢力に対する圧力団体として、軍産複合体は重要な役割を果たしている。ゆえに、軍産複合体を知ることは、ロシアの政治状況を理解するうえでも重要だ。本書では、航空機産業や造船産業、さらに、最大の軍産複合体、ロシアテクノロジー(Rostec)についても考察する。
終章では、ごく簡単なまとめを行う。ここで、サイバー空間をめぐる諸問題や「サイバー軍」について検討する。
ドナルド・トランプ大統領の登場で、米ロ関係だけでなく、米国とNATOの関係も揺さぶられることになるだろう。そうなれば、ここでの記述はすぐに時代遅れになってしまうのだろうか。本書はそうした事態を避けるために、できるだけ詳細に細部にこだわった分析を行っている。そうすることで、大きな変化をより理解することができると信じているからである。
なお、参考文献は本文中ないし註に挿入した。このため、参考文献一覧はあえて表示していない。本文中の括弧内で、新聞・雑誌などの掲載日を適宜、紹介している。
全体として、一般の方にはやや瑣末すぎるほど、詳細な分析があるかもしれない。しかし、「真実は細部にこそ宿る」のであって、こうした丹念な研究こそ必要であるというのが筆者のこれまで貫いてきた研究姿勢だ。逆に言えば、詳細で精緻な研究が少なすぎる。本当のロシアの姿に近づきたいと願う真摯な読者にお読みいただきたいと願っている。
最後に、本書の分量について説明しておく。全体で29万1921文字(スペースを含める)である。400字換算で730枚ほどになる。
2017年1月18日
塩原 俊彦
註
「はじめに」
(1) 日本語で読めるロシアの軍事研究には、小泉悠の『軍事大国ロシア』(作品社, 2016)がある。だが、読者にお薦めしようとは思わない。なんとかいう学会から書評を頼まれたが、無視した。なぜかと言えば、研究への誠実さが感じられないのである。筆者の恩師、故宮鍋幟は「ある言葉について調べるために1カ月かけて探しまわる」とよく言っていた。その教えにしたがって、筆者はできるだけ誠実に探究する努力をいとわないように努力してきたし、いまも努力している。こんな筆者からみると、あまりにも通り一遍の皮相な分析に嫌悪感すら覚える。とくに、グローバリゼーションのもとで、OECDやWTO
Roshia no Saishin Kokubou Bunseki (Japanese Edition)
Sobre
Baixar eBook Link atualizado em 2017Talvez você seja redirecionado para outro site