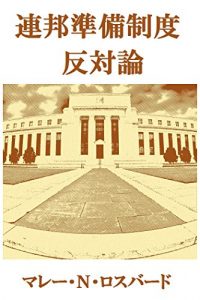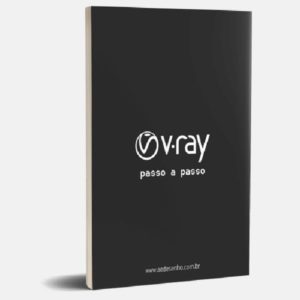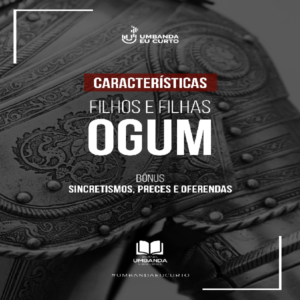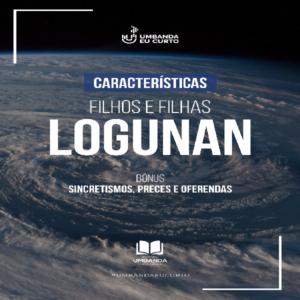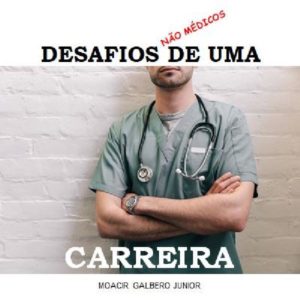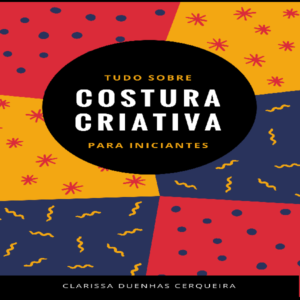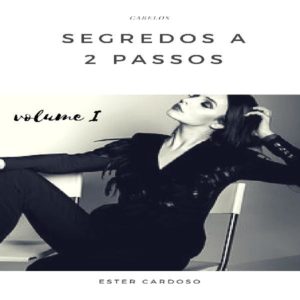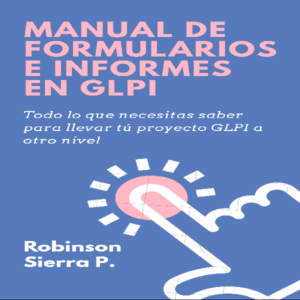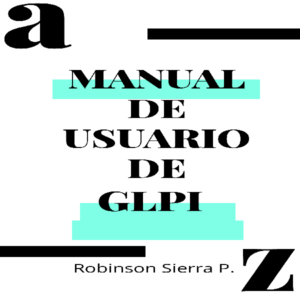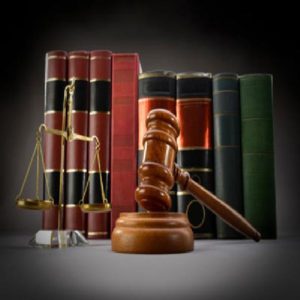本書はMurray N.Rothbard, The Case Against the Fed, Mises Institute, 1994を日本語に翻訳したものである。ロスバードの貨幣論や景気循環論についての著書は、吉田晴彦訳「人間、経済及び国家」の「第11章 貨幣とその購買力」、拙訳「政府は我々の貨幣に何をしてきたか」、同「アメリカの大恐慌」などがある。本書において、ロスバードは書名の通りその焦点をアメリカの連邦準備制度にあて、その成立前後の過程を追跡している。そして連邦準備制度そのものがインフレや景気循環を生み出していると批判してその廃止を求める。
本書の章立ては以下の通り。前半の章では貨幣がどのように出現してきて、金本位制度の確立に至り、更に現在のような法定不換紙幣に切り替わるプロセスと、そのために中央銀行と管理通貨制度が必要であることを論理的に説明している。後半の章ではアメリカの中央銀行である連邦準備銀行が設立されるまでと、設立後から世界恐慌発生までの歴史を追い、連邦準備制度設立の意図を明らかにしている。
・序論:貨幣と政治
・貨幣の起源
・貨幣の最適な量はどれだけか
・貨幣の膨張と偽造
・合法化された偽造
・貸付銀行業
・預金銀行業
・部分準備銀行家の問題:刑法
・部分準備銀行家の問題:支払不能
・好況と不況
・倉庫受領証の形
・中央銀行の登場
・銀行の信用拡大に対する制限の除去
・中央銀行による資産購入
・連邦準備銀行の起源:国内銀行制度の出現
・連邦準備銀行の起源:ウォール街の不満
・全面的なカルテル化:進歩的な方針
・中央銀行業を納得させる:運動の操縦 1897-1902
・中央銀行運動の復活:1906-1910
・ジキル島での最高の成果
・ついに連邦準備銀行:モルガンによって管理されたインフレーション
・ニューディールとモルガン家の解任
・預金「保証」
・連邦準備銀行の支配および通貨膨張の方法
・何をすることができるか
ロスバードは貨幣は自由市場で生じるもので、政府などが強制して始めるものではないという。物々交換の世界で市場性のある商品が貨幣となり、貨幣による間接交換が可能となったのだ。様々な商品が貨幣として選ばれたが、最終的に市場が選んだのは金と銀であった(『貨幣の起源』)。
ひとたび市場で貨幣が確立すれば、貨幣を増やす必要はない。一般の財であれば供給量が増えれば価格が安くなって生活が良くなる。しかし貨幣の場合は供給量が増えても貨幣の購買力が下がるだけで、社会に何の利益も与えない(『貨幣の最適な量はどれだけか』)。ロスバードのこの指摘は重要だ。昨今の政府がバラマキ政策を推奨するのは間違っているのである。
金本位制の下であれば、毎年の金の採掘量は耐久性のある金の総量と比べれば微量であるから、貨幣供給量は少しずつしか増えない、よって通貨価値は安定する。そして財の生産が増加すれば物価水準が下がって貨幣の購買力が大きくなり(実質賃金の増加)、貨幣の蓄積と投資を促進し、結果的に社会の生活水準が上昇する。(『貨幣の膨張と偽造』)これが自由な経済のあるべき姿だろう。もちろん価格の低下は不況を意味しない。電話やコンピュータなどの成長分野を見れば明らかだ。
ところが偽造(金による裏付けのない紙幣や預金)により貨幣供給量が増加すると物価が上がり偽造者に富を移すことになる。新しい貨幣の最初の受取人(正負関係者や政府と取引する者など)は、物価が上がる前に財を買うことができるので利益を得るが、後の受取人は価格が上がってから貨幣を受け取るので損をする。貨幣インフレーションは初期の受取人が後期の受取人から没収する隠れた税なのだ。
さて、貨幣の偽造はどのようにして行われるのか。ロスバードは倉庫業と銀行業を対比して説明する。倉庫業者は顧客から物品を預かり受領証を発行する。顧客が物品を受け取りたいときは、倉庫に行って保管料を支払い、受領証と引き替えに物品を受け取る。もし倉庫業者が物品を返却できないと言うなら、それは詐欺であって貸し倒れではない。また倉庫業者が預けたものとは別の物品を返すのも犯罪だ(預けた人が納得しない限り)。但し、小麦のように代替可能な物の場合には、倉庫業者は預かった小麦と1粒ずつ全く同じ小麦を返す必要はなく、預かったのと同じ等級で同じ量の小麦を返せばいい。銀行業も小麦を保管する倉庫と同じだ。業者は預かった金貨と全く同じ物を返さなくても、同じ額の金貨を返せば良い。
そこに問題が生じる。小麦を保管する業者が預かっている小麦を別の用途に流用すれば、それは詐欺・横領だ。小麦はいずれ引き出されるので、詐欺は発覚する。ところが銀行業の場合はそうならなかった。銀行に金貨を預けて受け取った受領証が、そのまま代替の貨幣として流通したのだ。よって金貨が引き出される事は少ない。そこで銀行は預かった金貨を流用したり、更に進んで受領証を偽造するようになった。後者の場合は家計供給量が増加するので、インフレーションを引き起こすことになる(『預金銀行業』)。
今の銀行が部分準備銀行と言われ、預金のほとんどを貸し出しのは詐欺でしかない。ロスバードは、これは刑法上も問題だし、取り付け騒ぎが起きるなどしたら銀行は必ず支払不能に陥ることを説明する(『部分準備銀行家の問題:刑法』、『部分準備銀行家の問題:支払不能』)。
インフレーションが起きるとそれによって利益を得る人と損失を被る人が生じ、後者のインフレに対する不満が増す。そして人々の取り付け騒ぎを恐れる銀行が信用を引き締め、景気が後退する。銀行による信用の拡大と収縮が景気循環の原因なのだ(『好況と不況』)。
銀行は不況期に陥ることなく信用を拡大させたがった。そのためには「最後の貸し手」としての中央銀行が必要であった。銀行に貨幣を融通する中央銀行があれば、取り付け騒ぎの危険性は激減する。更に中央銀行が貨幣の発行を独占し、すべての国内の銀行をその支配下に置いて銀行カルテルを結成すれば、その体制が確立する。
アメリカでは1913年に制定された連邦準備法に基づき、連邦準備銀行が設立された。この背後にはモルガン家の暗躍があり、以後も連邦準備銀行を通したモルガン家のアメリカ金融支配が続くことになる。第一次世界大戦中に連邦準備制度はアメリカ国内の通貨発行量を2倍にし物価を2倍にしたが、アメリカ自身の参戦と、イギリスなどの同盟国への巨額の貸付を可能にした。
1929年に世界恐慌が発生するが、それについては本書では余り触れられていない。詳細はロスバード著、拙訳「アメリカの大恐慌」を参照して欲しい。
1933年と1935年にニューディール銀行法が制定され、連邦準備銀行の力が政府に移され、モルガン家の金融支配が覆され、その支配力はロックフェラー、ハリマン、リーマン・ブラザーズ、ゴールドマン・サックス、等々に移る。
1933年にはアメリカ国内での連邦準備紙幣・預金と金貨との兌換が中止され、1971年のニクソン・ショックで、外国とのドルと金の兌換を停止して現在に至っている。
連邦準備銀行設立以来、インフレーションは激しくなり、不況はずっと深刻になった。原因となっている連邦準備制度を廃止し、金本位制度に復帰すべきだとロスバードは言う。連邦準備銀行の資産を清算して債権者に比例して分配すればいいのだ(『何をすることができるか』)。
このようにロスバードは連邦準備制度に反対してその廃止を訴える。ロスバードの主張の多くはアメリカの連邦準備制度だけではなく、他の先進資本主義国の中央銀行にも当てはまる。中央銀行を廃止し、中央銀行を頂点とした国内の銀行カルテルを解体すべきである。そして健全な貨幣制度である金本位制に復帰する。そうすれば我々はインフレや景気循環に悩まされることなく、より安定して豊かな生活を送ることができるだろう。
ネットを見ていると「金本位制は時代遅れだ」という人がよくいる。時には「法定不換紙幣は、富を無限に増やすことができる『打ち出の小槌』だ」とまで言い、そして「管理通貨制度は政府が正しく貨幣を管理する仕組みなのだから問題は生じない」と言い切る人さえいるから、本当に唖然としてしまう。
とはいえ訳者の手元にある何冊かの金融関係の本を見ても「管理通貨」「信用創造」の利点のみしか書かれていなかったりする。ロスバードの言う貨幣論には一切言及していない。そういう状況であるから、真実を見ることができず政府や銀行にすっかり騙されている人が多いのも仕方がない。少しでも本書を手にした人が真実に開眼するよう期待したい。
The Case Against the Fed (Japanese Edition)
Sobre
Baixar eBook Link atualizado em 2017Talvez você seja redirecionado para outro site