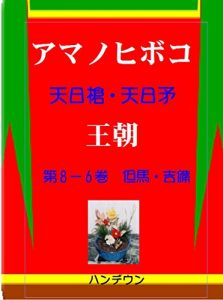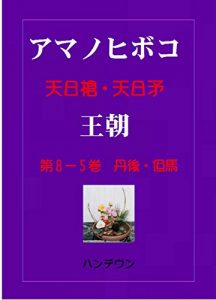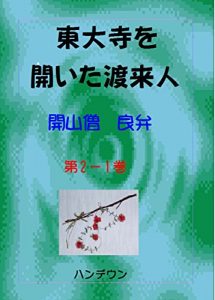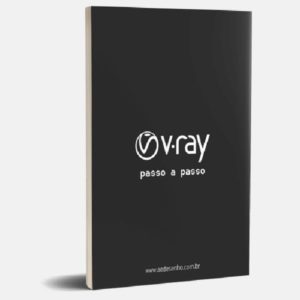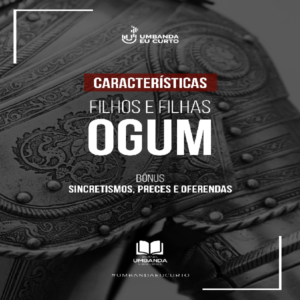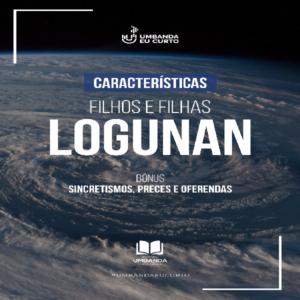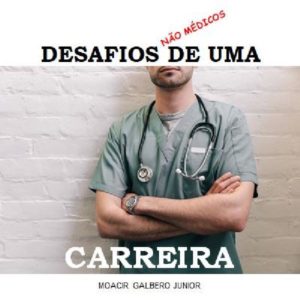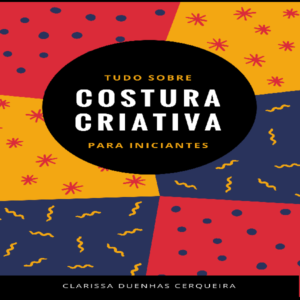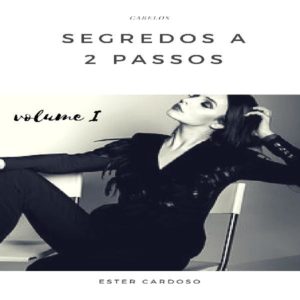アマノヒボコ王朝 6 但馬・吉備
★大和百済王朝以前にアマノヒボコ(天日槍・天日矛)新羅王朝が存在した。倭国には、遠い昔から強固な朝廷が存在していたという〝幻の大和朝廷〟論に欺かれてはならない。
〔本書の基本史観〕
◎自分探しの旅は、先祖探しの旅になり、歴史への旅となった。その途上、日本古代史の数々の偽造に気づいた。どうして、そうなるのか。その疑問を解き明かす熱情の旅になった。
◎日本列島は紀元前後、14、5世紀のアメリカ大陸や17、8世紀のオーストラリア大陸のように原住民(縄文人)しか住まない新天地だった。その新天地を、韓半島からの渡来人(弥生人)が開拓していった。
◎しかし、そうした渡来人の活躍は闇に葬られてきた。先祖を隠蔽したそのような歴史は砂上の楼閣に過ぎず、先祖を元のあるべき姿へ復元しなければならない。それが、現代に生きる子孫の果たすべき役割と信じる。
〔序言〕
自分は何者なのか。在日韓国人として、なぜ日本で生まれなければならなかったのか。その青春の疑問から、いつしか歴史の旅が始まった。『日本書紀』に目を通したとき、実に訳のわからない書だったが、韓(朝鮮)半島関係の記述が多く、〝朝鮮書紀〟じゃないかと思ったくらいだ。縄文人しか住んでいなかった当時の日本列島は、14、5世紀のアメリカ大陸や17、8世紀のオーストラリア大陸のように原住民しかすまない新天地でり、韓半島からの渡来人(弥生人)は日本列島に定住、開拓していったのだ。
そうした痕跡を探し求めるため、実に多くの書を読破した。しかし、韓(朝鮮)半島との親密な関係を論述する書はほとんどなく、多くは日本が韓(朝鮮)半島支配していたという倒錯の論考である。歴史は人間の営みであって、神業の賜物ではない。新井白石は「神は人なり」と喝破したように、神業の史実を作り出してはなるまい。が、本居宣長など多くの研究者は、韓半島との関係に論述せず、神業の史実を多用した。〝存して論ぜず〟は、神業の史実を論じるなという教えであり、それがため、多くの人が歴史を正視せずして、とんでもないことを正当化している。罪深きことである。
自分自身の淵源を訪ねる歴史旅の途上、『日本書紀』自体が偽造の書であることを知り、その『日本書紀』の記述を正当化せんがための論考が拡大生産されて、日本はまさに、韓半島との関係を断ち切った〝歴史偽造大国〟になっている。それは、先祖に対する冒涜であり、神に対する冒涜でもある。日本人自身がそうした偽造を正していかなければならないにもかかわらず、経済的利益を優先するあまり、歴史偽造を拡大再生産して、韓国併合という罪業まで敢行した。真の歴史を探求していくことこそが韓日親善を定立する礎であると信じる。
奇しくも日本に生まれた在日韓国人として、韓半島にルーツを持つ者として、闇に葬られた先祖の事績を正しく検証し、復元したいという熱情にかられた。それは、自分が何者かという青春の疑問に対して、回答を求める旅であり、遠く古代にまでつながるであろう自分探しの旅であり、先祖に感謝する旅でもある。自分が何者かを知りたいと思ったら、本書を熟読していただきたい。その前に『日本書紀』を通読されることをお勧めする。
目次
〔91〕 須義(すぎ)神社 兵庫県豊岡市出石町荒木273
〔92〕 御出石(みいずし)神社 兵庫県豊岡市出石町桐野986
〔93〕 日出(ひで)神社① 兵庫県豊岡市但東町南尾189
〔94〕 日出(ひで)神社② 兵庫県豊岡市但東町畑山329
〔95〕 比遅(ひち)神社 兵庫県豊岡市但東町口藤547
〔96〕 須流(する)神社 兵庫県豊岡市但東町赤花字主楼谷632
〔97〕 鷹貫(たかぬき)神社 兵庫県豊岡市日高町竹貫429
〔98〕 多摩良伎(たまらき)神社 兵庫県豊岡市日高町猪ノ爪367
〔99〕 気多(けた)神社 兵庫県豊岡市日高町上郷227
〔100〕 大与比(おおよい)神社 兵庫県養父市三宅392-1
〔101〕 杜内(もりうち)神社 兵庫県養父市森919
〔102〕 養父(やぶ)神社 兵庫県養父市養父市場
〔103〕 斎(いつき)神社 兵庫県養父市長野265
〔104〕 佐伎都比古阿流知命(さきつひこあるちのみこと)神社 兵庫県朝来市和田山町寺内435
〔105〕 大避(おおさけ)神社 兵庫県赤穂市坂越1299
〔106〕 児島高徳(こじまたかのり)墓 兵庫県赤穂市坂越
〔107〕 児島湾大橋(こじまわんおおはし) 岡山市南区飽浦
あとがき
まえがき
アマノヒボコが最後に定住した地の但馬は、円山川(まるやまがわ)の流域である。朝来市生野町円山(標高641.1m)に源を発して北流、養父市、豊岡市を流れ、日本海に注ぐ。朝来川(あさごがわ)とも呼ばれている。円山川の中核都市は現在、豊岡市だが、往古は新羅王子天日槍(アマノヒボコ)を祀る出石神社が鎮座する出石の地であったろう。というのも、円山川河口付近は川の氾濫に悩まれた地であったろうからだ。
その但馬の地を開拓したのがアマノヒボコ一族であり、各地に伝承が残る。御出石(みいずし)神社が鎮座する現在の豊岡市出石町桐野の地は、ヒボコが最初に居住したとされる。祭神のイズシオトメ(伊豆志袁登売神)は、アカルヒメ(阿加流比売神)あるいはシタテルヒメ(下照比売神)の別名と考証されている。いずれにしても、ヒボコの妻とされている女性である。
ヒボコの入植は150年頃と思われるから、その頃の倭地は原住民(縄文人)が住むだけの荒蕪の地であったと思われる。そこへ、弥生文化を携えたヒボコ一族が入植し、円山川の氾濫を抑制し、稲文化を定着させたと思われる。そして、アマノヒボコ王朝を樹立し、地域を開拓したのであろう。
なぜ、そう考えられるのか。14、5世紀のアメリカ大陸はインディアンしか住まない新天地であり、イギリスからの入植者が開拓を始めた。17、8世紀のオーストラリア大陸は原住民アボリジニの居住地であったが、イギリスからの囚人らによってがまずは開拓された。それより1000年以上も前の日本列島は、縄文人の楽園であったが、韓半島からの弥生人の入植により、開拓されたのである。
確かな証拠がないと反撃する御仁もたくさんいるだろうが、識者によって発表されている弥生文化と縄文文化の断絶などの説がなによりの証拠だ。その一環として、ヒボコの但馬開拓の伝承などがあるのだ。
そうした地を訪ねる歴史探訪であるが、限られた時間内にくまなく回るのは困難だ。で、省略した箇所もかなりあるが、この第6巻は、但馬の続編である。
〔91〕 須義(すぎ)神社 兵庫県豊岡市出石町荒木273
須義は「すげ」とも「すぎ」とも訓まれ、いま菅八幡と称して、豊岡市出石町荒木に鎮座する。出石城を挟んで、諸杉神社の反対、西側である。出石町から八鹿町へ向かう幹線道路から脇道に入ると、「式内須義神社」という石造りに立派な神号が目に入り、その横に小さく「出石町指定文化財須義神社本殿」という標柱があった。
その奥に鳥居があり、鳥居の奥に長い石段が上のほうに伸びていた。祭神は菅竈由良度美(すがかまどのゆらとみ)神で、誉田別神(応神天皇)を配祀している。「菅谷史跡マップ」という大きな案内地図があって、多田弥太郎顕彰碑、観音寺池、しみずけの水、荒木高山城跡、須義神社、大銀杏、天然記念物鶴山鶴蕃殖地記念碑、鶴山などが記されていた。鶴山はコウノトリの営巣地として有名である。
『地名辞書〈但馬国〉』に「須義は菅とよみ、天日槍の裔孫の居邑なるべし(中略)酢鹿とあるは菅に同じ、今も荒木の里を菅谷という」とある。酢鹿というのは、ヒボコ6世孫の酢鹿之諸男(すかのもろお)のことで、妹にユラトミ(菅竃由良度美)がいる。「菅竃」は「菅浜」の約で、「由良」は、丹後・伯耆・隠岐・丹波・淡路・伊予・讃岐・土佐・紀伊に広がる地名である。「度」は「の」を意味し、「美」は「神」を意味するという。
須義神社は、社伝によると、応神天皇40年の創祀だが、別伝では、神功皇后が熊襲征討のため出石神社に戦勝祈願をした時だという。祭神にも諸説があり、『神名帳考證』では多遅摩母呂須玖とあり、多遅摩母呂須玖は天日槍の子で、菅竈由良度美は、多遅摩母呂須玖の妹あるいは娘とされる。『但馬国神社燈明記』では須義毘古命、『国司文書別記』では須義命、『但馬神社重宝記』では須義芳男命ならび荒木帯刀部命、『特撰神名蝶』では習義朝臣の氏人が祖ニギハヤヒ(饒速日命)を祀ったという。
谷川健一氏によれば、「菅」と呼ぶ地名は、「洲処(すか)」であり、砂鉄のとれるところを指す。菅のつく地名としては、兵庫県宍粟郡安富町菅谷、島根県飯石郡吉田村菅谷、滋賀県蒲生郡菅田、群馬県大田市菅の沢、長崎県南高来郡有明町菅などがあり、皆たたら(炉)などの製鉄遺跡があったところである。
『新撰姓氏録』によれば、「菅田首」があり、その祖は「天久斯麻比止都命(天目一箇命)の後なり」という。天目一箇命は、「葦田神社」の項でみたようにヒボコ(天日槍)の随神で、水銀中毒に苦しんだ鍛冶の神であった。鍛冶族は片目で鉄の溶け具合や火色などを卜定したことから目卜(まうら~真浦)と称し、『旧事紀〈天神本紀〉』に「倭鍛師等の祖は天津真浦なり」と記されている。
Amanohiboko Ouchou 6 (Japanese Edition)
Sobre
Baixar eBook Link atualizado em 2017Talvez você seja redirecionado para outro site