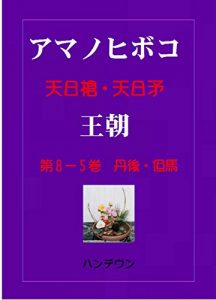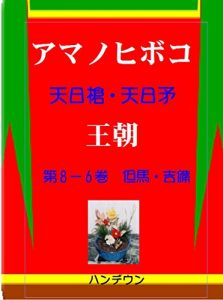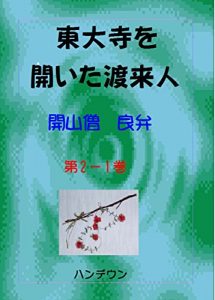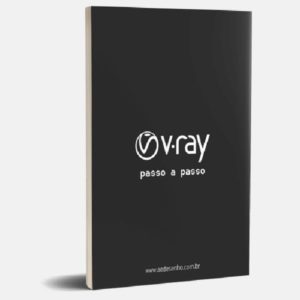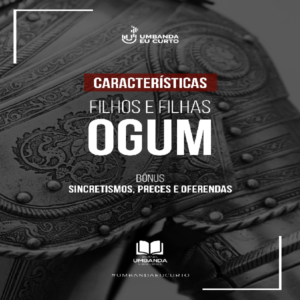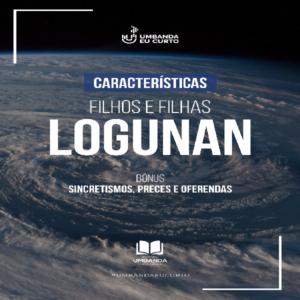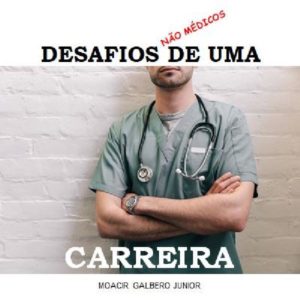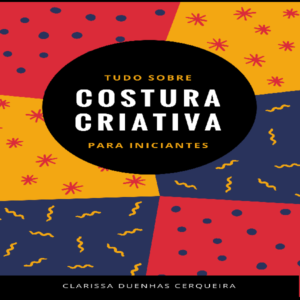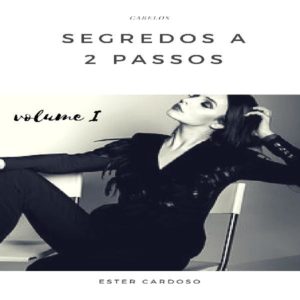まえがき
本シリーズ全3巻で、この第3巻が最終巻になるが、1・2巻での大山祇を祭神とする各地の神社探訪によって、大山祇=賀茂建角身=大己貴=丹波道主=天日槍=賀茂別雷=彦火明命=饒速日=という関係になることを突き止め、塩土老翁=椎根津彦=珍彦という関係から、神武帝は九州からの東征ではなく、丹波からの南遷という結論を得た。それは、大和朝廷以前の王朝の存在を示唆するものである。
大和朝廷は初代神武帝から大和(奈良県)に創建され、以来、万世一系の天皇家によって維持され、巨大な朝廷が常に大和にあったというのが通説である。しかし、『日本書紀』を熟読していけば、そのような大和朝廷が存在していたという形跡は感じられない。特に神武帝に続く欠史8代の朝廷がそうである。
神武帝が新羅系王朝であることは、本シリーズでも何度となく述べてきた。拙著『アマノヒボコ王朝 第1~8巻』『東大寺を開いた渡来人 第1~2巻』(いずれもKindle本)でも随所に示唆している。
大和朝廷は、高句麗広開土王によって撃破された沸流百済王朝がそのまま日本(倭地)に亡命した後に樹立された王朝である。その沸流百済王朝も当初は河内王朝といっても過言ではない。
このように、日本の古代史は実に謎が多い。他国では考えられないことであろう。日本の正史と称される『日本書紀』であるが、日本国の生成過程が著述されているのかと思ったら、そうではなかった。あまりにも朝鮮(韓半島)関係の記事が多いのである。筆者は、現代語訳ではあるが、『日本書紀』を最初に読んだときの感想だ。まるで『朝鮮書紀』ではないかと疑った。
それに、登場してくる神々の行動もしまりがなく、尻切れトンボで、何のつながりもない。実に難解な神々だった。が、しかし、その神々を、根気強く、あらゆる角度から追い求めていくと、その実像が浮かび上がってくることに気づいた。そのキーワードは各地に鎮座する神社の由緒や伝承である。
そうした作業を積み上げてまとめたのが、本シリーズであるが、「乎知の郡。御嶋。坐す神の御名は大山積の神、一名は和多志の大神なり。是の神は、難波の高津の宮に御宇しめしし天皇の御世に顕れましき。此神、百済の国より渡り来まして、 津の国の御嶋に坐しき。御嶋と謂うは、津の国の御島の名なり」という『伊予国風土記〈逸文〉』の記述が本シリーズのはじまりである。
日本の古代史の謎は、日本人自らの出自を韓半島から切り離したことからくるギャップというものだろう。
現在の通説は、日本人は縄文時代からこの日本列島に自生してきた種族だということで、日本人の原郷を縄文時代に求めようとする思考が主流だ。しかし、弥生文化は縄文文化を継承したものでないことは、遺跡・遺物等からもはっきり立証されているし、医学的にも縄文人と弥生人は別個の種族だと証明されている。
そうしたことを無視してしまうには、歴史の偽造しかない。ゆえに、日本は歴史偽造大国だといっても過言ではない。その嚆矢が、いうまでもなく『日本書紀』だ。『日本書紀はなぜ偽造されたのか』などの図書が出版されているのをみても明らかだろう。
江戸時代になると、本居宣長が『古事記伝』を著作して、その博識ぶりが高く評価されているが、この書も、歴史偽造に一役かっているといってもいいだろう。国学の四大人(こくがくのしたいじん)といわれる荷田春満・賀茂真淵・本居宣長・平田篤胤の思想が、明治維新に受け継がれ、征韓論生成の源となり、韓国併合に突き進んで行く。
それがため、歴史の偽造がさらに進んだ。石上神宮所蔵七枝刀や高句麗広開土王碑が改竄されたとは諸書が指摘している。植民地時代は、多くの朝鮮図書が日本に略奪されたというし、朝鮮を矮小化するための歴史書が、朝鮮総督府主導で数々刊行されたといわれている。
本シリーズは、せめても、あるべき姿の歴史を追い求めた書である。今回のテーマは「大山祇は武寧王か」だが、第3巻では、紀州、山城、吉備、美濃、尾張、相模、吉備、安芸、長州、筑紫と幅広い探訪になったが、その答えは求められるだろうか。 2016年2月
まえがき
〔22〕 隅田八幡(すだはちまん)神社 和歌山県橋本市隅田町垂井622
国宝の人物画像鏡を吏読(イド)で読む
百済と倭の共通の祖国は辰
武寧王は加唐島(佐賀県唐津市)で生まれたがゆえに島王
軍君という名の百済昆支王は雄略帝?
〔23〕 吉備津(きびつ)神社 岡山県岡山市北区吉備津931
大王陵に匹敵する造山古墳や作山古墳
吉備は事実上伽耶の国にほかならない
吉備津彦=五十狭芹彦=笥飯(気比)大神=去来紗(伊奢沙)別=天日槍
〔24〕 日吉(ひよし)大社 滋賀県大津市坂本5-1-1
大物主=饒速日=大山咋=大山祇
最澄は入唐求法のとき航路の安全を気比神(天日槍)に祈請
比叡山延暦寺境内に新羅豪商・張保皐の顕彰碑
〔25〕 松尾(まつお)大社 京都市右京区嵐山宮前3
賀茂氏の男が秦氏の聟になった
秦宿禰・秦忌寸らが惟宗朝臣に改姓、薩摩島津家・対馬宗家も惟宗氏
〔26〕 大山阿夫利(おおやまあふり)神社 神奈川県伊勢原市大山355
奈良東大寺の開山僧良弁が開創した大山寺
アフリ(阿夫利)はアカラ(大加羅)
〔27〕 大山(おおやま)神社 岐阜県加茂郡富加町大山218
紀州の南方熊楠が大山神社の合祀に憤慨
〔28〕 多加意加美(たかおがみ)神社 広島県庄原市口和町向泉973
高寵(たかおかみ)=大名持(大己貴)=大蛇=大山祇
〔29〕 石城(いわき)神社 山口県光市塩田石城2233
防長の古代大族はみな天日矛かその同族たる天孫族の後裔
〔30〕 恒見八幡(つねみはちまん)神社 福岡県北九州市門司区恒見町3-1
宇佐八幡宮から勧請して奉祀
〔31〕 河守(こうもり)神社 福岡県遠賀郡水巻町吉田東3-1-1
日本全国いたるところで大雨のたびに洪水
〔32〕 伊多波刀(いたはと)神社 愛知県春日井市上田楽町3454
阿智から出た苗字には「味(アヂ)」がある
〔33〕 市原稲荷(いちはらいなり)神社 愛知県刈谷市司町8-52
木花之聞耶姫(このはなのきくやひめ)もいる
〔34〕 三嶋(みしま)大社 静岡県三島市大宮町2-1-5
三嶋神は東海随一の神格、源家再興を祈願
三島木綿 肩にとりかけ われ韓神の
〔35〕 岡田鴨神社 京都府木津川市加茂町北鴨村44
日月星辰を祭り山海河津を祀るというのは歴史を解しない妄説
大山祇の子孫が武寧王を主(あるじ)と仰いだ?
あとがき
あとがき
大山祇は、斯麻(島)王と称された百済25代武寧王なのか。このテーマのもと、各地の神社をめぐり、最終回の稿をまとめる段になったが、隅田八幡神社(和歌山県)の探索では、武寧王が扶余出身の百済大王であり、その扶余は、百済と倭の共通の祖国である辰韓を出自としていることを突き止めた。
しかし、ここで大きな疑問が生じるのは、海を隔てた百済の地の王がどうして倭国の神様に祭り上げられなければならないのか、ということだ。海運を担う三島氏が百済の武寧王を、倭国では大山祇(積)と称して、権威を振りかざしていたのだろうか。それにしても大山祇がどうして、武寧王でなければならないのか。
百済の大王は武寧王以外にも、東城王もいれば、聖明王もいる。文献上からは、倭国から帰国して百済の大王になった東城王や倭国に仏教を伝えた聖明王のほうが、武寧王よりもはるかに倭国との関係が深い。なのにどうして武寧王なのか。武寧王の何かが隠されているのか。
昆支王が渡来したのは、雄略帝5年である。そのときは5人の子供を従えていた。その一人が百済に帰って大王になった東城王であり、他の一人は継体帝である。斯麻王は生まれてすぐ帰されたのではなく、昆支王に伴われて、実の子供のように育てられ、倭国で成長していったのだ。そして、三島氏族を組織し、百済と倭国の海運を掌握し、制海権を確保したものと思われる。
筆者は雄略帝=昆支王ではないかと考えている。でなければ、昆支王の子である東城王を百済の大王にできるはずがないからだ。隣国の王の指示で、その国の王にする国が、どこにあろうか。いつの世にも、そのような国はなかろう。
そうした状況の中で、有能な斯麻王=武寧王は、昆支王の意図のもと、百済支援軍として三島氏族(三島軍団)を組織し、三島神=大山祇神と称されたのであろう。金達寿さんがいう「百済人集団の首長」というのが、三島氏族を組織した斯麻(島)王=武寧王ということになろう。
また、武寧王は、その墓誌から、辰朝人とされており、遠い昔は辰韓出身であった。塩土老翁=亦名住吉同体=大綿津見神=亦名豊受大神が大山祇=和多志大神も辰韓出身であったと考えられる。同族であるからこそ、身を挺して護衛することができると思われるからだ。
しかしながら、武寧王は500年前後の存在であり、日本創生の神と崇められる大山祇はそのはるか以前の存在であると思われるから、大山祇=武寧王とするわけにはいかない。二つの百済論、つまり沸流百済と温祚百済があり、高句麗広開土王に撃破されて倭地に逃走した沸流百済の都邑地熊津を、後に温祚百済(漢城百済)が遷都し、百済と称して沸流百済を継承したため、沸流百済と温祚百済の見分けがつ
Kudara kara toraisita Ooyamtumi wa Buneiou ka (Japanese Edition)
Sobre
Baixar eBook Link atualizado em 2017Talvez você seja redirecionado para outro site