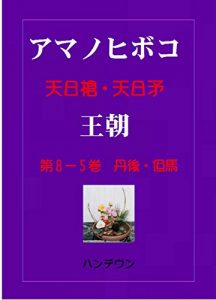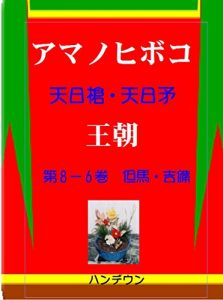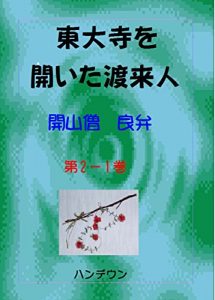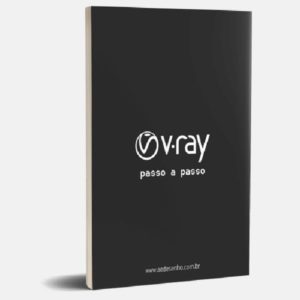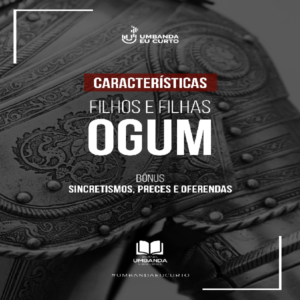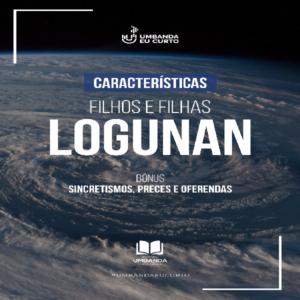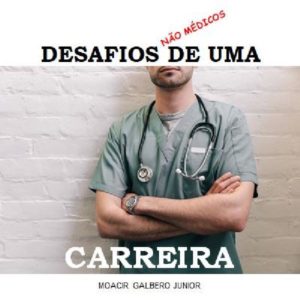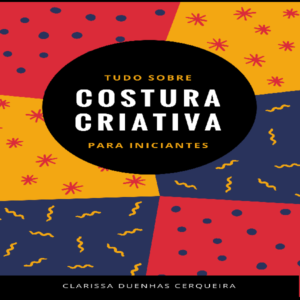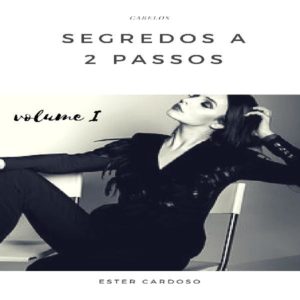〔序言〕 日本全国いたる所に鳥居があります。その鳥居のある風景は、日本の原風景といえるでしょう。鳥居とは、読んで字のごとし、〝鳥が居る〟ところでしょう。ならば、どうして鳥が居るのでしょうか。韓半島には古来、〝天下大将軍〟〝地下女将軍〟と墨書されているチャンスンと、ソテと呼ばれる鳥の形象物を先端につけた木竿とのセットが、村の入口に建てられて、ソテの鳥が見張り役で、チャンスンに報告し、悪鬼や悪霊の侵入を防いだということです。日本では大阪府池上遺跡などから鳥形木製品が出土したことから、初期の鳥居には鳥の形象物が笠木(門の上においた横木)の上にあったと見られています。鳥居を立てて境界をはっきりさせて、よそ者が入らないようにしたのです。その鳥居はソテが発展したものといわれています。
鳥居のある風景 7 岡山 広島 山口 島根 目次
まえがき
〔241〕 吉備津神社
〔きびつじんじゃ〕 岡山県岡山市北区吉備津931
吉備津神社 鳴釜は楽浪国の自鳴鼓(チャミョンゴ)とどこか似ている
〔242〕 吉備津彦神社
〔きびつひこじんじゃ〕 岡山市北区一宮1043
吉備津彦神社 吉備津彦=五十狭芹彦=笥飯(気比)大神=去来紗(伊奢沙)別=天日槍
〔243〕 作楽神社
〔さくらじんじゃ〕 岡山県津山市神戸433
作楽神社 渡来人子孫と知って児島高徳を忠臣に祭り上げた?
〔244〕 児島高徳墓所
〔こじまたかのりぼしょ〕 兵庫県赤穂市坂越
児島高徳墓所 児島高徳は新羅王子天日槍の後裔三宅範長の娘を母に誕生
〔245〕 出雲大社美作分院
〔いずもたいしゃみまさかぶんいん〕 岡山県津山市田町87
出雲大社美作分院 播磨~美作~伯耆~出雲を横断する出雲街道
〔246〕 中山神社
〔なかやまじんじゃ〕 岡山県津山市一宮695
中山神社 もともとはニギハヤヒの子孫が奉祭した神社?
〔247〕 阿智神社
〔あちじんじゃ〕 岡山県倉敷市本町12-1
阿智神社 応神朝に百済から渡来した阿智使主の一族が奉斎
〔248〕 大野見宿禰神社
〔おおのみすくねじんじゃ〕 鳥取市徳尾80
大野見宿禰神社 相撲の神さま野見宿禰は古墳に埴輪を立てた
〔249〕 樗谿神社
〔おうちだにじんじゃ〕 鳥取市上町87
樗谿神社 子供は石を投げ合い若者は刀槍で殺し合う遊びに朝鮮通信使もびっくり
〔250〕 高諸神社
〔たかもろじんじゃ〕 広島県福山市今津町519
高諸神社 実際の祭神は〝劉仁軌の乱〟を逃れてきた新羅国王
〔251〕 小烏神社
〔こがらすじんじゃ〕 広島県福山市鞆町後地
小烏神社 三原刀匠の先祖は〝小烏〟という官位を持つ新羅人だった?
〔252〕 沼名前神社
〔ぬなくまじんじゃ〕 広島県福山市鞆町後地1225
沼名前神社 縄文人は第1次渡来者、弥生人は第2次渡来者
〔253〕 亀山神社
〔かめやまじんじゃ〕 広島県呉市清水1-9-36
亀山神社 八幡神が豊後国姫島、安芸国栃原を経て宮原村亀山に遷座
〔254〕 多加意加美神社
〔たかおかみじんじゃ〕 広島県庄原市口和町向泉973
多加意加美神社 高オカミ=大名持(大己貴)=大蛇=大山祇
〔255〕 佐々井厳島神社
〔ささいいつくしまじんじゃ〕 広島県安芸高田市八千代町佐々井
佐々井厳島神社 沖の島を本拠とする宗像族と志賀島を本拠とする阿曇族
〔256〕 大山祇神社
〔おおやまづみじんじゃ〕 愛媛県今治市大三島町宮浦3327
大山祇神社 皇国史観に汚染された史観にうんざり
〔257〕 石城神社
〔いわきじんじゃ〕 山口県光市塩田石城2233
石城神社 神籠石は高句麗に源をもつ韓半島の山城
〔258〕 忌宮神社
〔いみのみやじんじゃ〕 山口県下関市長府宮の内町1-18
忌宮神社 アマノヒボコの子孫イトテ(五十迹手)の出迎え受けた仲哀帝
〔259〕 赤間神宮
〔あかまじんぐう〕 山口県下関市阿弥陀寺町4-1
赤間神宮 松雲大師が安徳祠の慶弔詩、以来朝鮮通信使の恒例に
〔260〕 彦島八幡宮
〔ひこしまやわたみや〕 山口県下関市彦島迫町5-12-9
彦島八幡宮 伊蘇=伊都は伊西(慶尚北道伊西面)のこと
〔261〕 熊野大社
〔くまのたいしゃ〕 島根県松江市八雲町熊野2451
熊野大社 クシミケヌ(櫛御気野)とスサノオ(素盞鳴)は同一神
〔262〕 八重垣神社
〔やえがきじんじゃ〕 島根県松江市佐草町227
八重垣神社 「八雲立つ」の歌は妻問いではなくスサノオの戦勝歌
〔263〕 忌部神社
〔いんべじんじゃ〕 島根県松江市東忌部町957
忌部神社 フトタマの子ヒワシ(天日鷲)はフツヌシ(経津主)の別名
〔264〕 玉造湯神社
〔たまつくりゆじんじゃ〕 島根県松江市玉湯町玉造522
玉造湯神社 櫛明玉はアマノヒボコの随神アマノマヒトツ(天目一箇)
〔265〕 神魂神社
〔かもすじんじゃ〕 島根県松江市大庭町563
神魂神社 神魂=熊野でその淵源は檀君神話の熊
〔266〕 売布神社
〔めふじんじゃ〕 島根県松江市和多見町81
売布神社 売布神は物部氏の祖神ニギハヤヒの後裔
〔267〕 武内神社
〔たけうちじんじゃ〕 島根県松江市八幡町303
武内神社 応神帝の子と武内宿禰の子が名前を交換
〔268〕 佐太神社
〔さだじんじゃ〕 島根県松江市鹿島町佐陀宮内73
佐太神社 出雲の加賀の潜戸で生まれた猿田彦は〝神在り〟の主宰者
〔269〕 美保神社
〔みほじんじゃ〕 島根県松江市美保関町美保関608
美保神社 鶏や卵を食べないのは忌避ではなく鶏林(新羅)を尊崇しているから
〔270〕 出雲大社
〔いずもおおやしろ〕 島根県出雲市大社町杵築東195
出雲大社 アマホヒ(天穂日)の子孫の出雲国造家が歴代の奉斎者
〔271〕 須佐神社
〔すさじんじゃ〕 島根県出雲市佐田町須佐730
須佐神社 出雲には意宇氏系と出雲氏=神戸氏系の二流
〔272〕 日御碕神社
〔ひのみさきじんじゃ〕 島根県出雲市大社町日御碕455
日御碕神社 稲佐の浜、日御碕海岸、北浦海岸に竜蛇がやってくる
〔273〕 須我神社
〔すがじんじゃ〕 島根県雲南市大東町須賀260
須我神社 スサノオの「八雲立つ」の歌は辰韓の言葉で詠まれもの
〔274〕 大飯彦命神社
〔おおいひこのみことじんじゃ〕 島根県江津市松川町太田199
大飯彦命神社 ツヌガアラシトはこの地で牛耕を教え田を拓いた
〔275〕 佐々布久神社
〔ささふくじんじゃ〕 島根県安来市広瀬町石原582
佐々布久神社 大和の都が危険で伯耆に移ったというが?
〔276〕 苗村神社
〔なむらじんじゃ〕 滋賀県蒲生郡竜王町綾戸468
苗村神社 那牟羅彦・那牟羅姫はアマノヒボコの眷属?
〔277〕 惟喬親王陵
〔これたかしんのうりょう〕 滋賀県東近江市永源寺町君ヶ畑
惟喬親王陵 皇位を継げず深山幽谷を流浪した惟喬親王
〔278〕 福泊神社
〔ふくどまりじんじゃ〕 兵庫県姫路市的形町福泊402
福泊神社 韓泊→唐泊、韓津→唐津、韓国神社→辛国神社などは〝韓かくし〟
〔279〕 国魂神社
〔くにたまじんじゃ〕 三重県津市西古河町23-26
国魂神社 高句麗系種族が大和を平定、国魂神も結局は渡来神
〔280〕 月読神社
〔つきよみじんじゃ〕 京都府京田辺市大住池平31
月読神社 大嘗祭で天皇が座るのは隼人の編んだ籠
あとがき
まえがき
写真紀行『鳥居のある風景』シリーズ第7弾は、〝岡山・広島・山口・島根〟です。補遺として書き漏らした所を若干加えました。
崇神朝に、四道将軍の一人として、吉備津彦が西海に派遣されました。はたしてそうでしょうか。『日本書紀〈雄略紀〉』における吉備下道臣前津屋の誅殺譚や吉備上道臣田狭の排除譚などを見ますと、その時期、雄略帝(大和政権)に対抗しうる一大勢力が吉備にあったことがわかります。であれば、吉備津彦は、派遣されたのではなく、その地域の国主(王)であったのではないでしょうか。
吉備津彦は、第7代孝霊帝の第3王子とされ、五十狭芹彦(=吉備津彦)という名で、吉備津彦=五十狭芹彦=笥飯(気比)大神=去来紗(伊奢沙)別=天日槍という関係になり、アマノヒボコと同人(神)格です。くわしくはハンデウン著「アマノヒボコ(天日槍)王朝」(Kindle版1~8巻)をご一読ください。ということは、大和朝廷以前に、アマノヒボコ王朝があったことの証左といえましょう。
「古墳文化という新しい文化の展開と軌を一にする崇神王朝の成立、初期ヤマト国家の成立を、朝鮮半島からの新たな文化的刺戟をぬきにしては考えられないとすれば、イリ王朝の成立は明白に渡来系種族による覇権掌握を示唆する」などと考証されていますように、大和朝廷の成立は、紀元660年に神武帝が即位したという遠い過去のことではありません。神武東征は虚構譚といわれています。大和朝廷以前の吉備津彦(=アマノヒボコ)の頃は、アマノヒボコ王朝が吉備、若狭、丹後、但馬などに存在していたのです。
『日本書紀』は、〝言葉明瞭、意味不明〟の
鳥居のある風景 7 岡山 広島 山口 島根 目次
まえがき
〔241〕 吉備津神社
〔きびつじんじゃ〕 岡山県岡山市北区吉備津931
吉備津神社 鳴釜は楽浪国の自鳴鼓(チャミョンゴ)とどこか似ている
〔242〕 吉備津彦神社
〔きびつひこじんじゃ〕 岡山市北区一宮1043
吉備津彦神社 吉備津彦=五十狭芹彦=笥飯(気比)大神=去来紗(伊奢沙)別=天日槍
〔243〕 作楽神社
〔さくらじんじゃ〕 岡山県津山市神戸433
作楽神社 渡来人子孫と知って児島高徳を忠臣に祭り上げた?
〔244〕 児島高徳墓所
〔こじまたかのりぼしょ〕 兵庫県赤穂市坂越
児島高徳墓所 児島高徳は新羅王子天日槍の後裔三宅範長の娘を母に誕生
〔245〕 出雲大社美作分院
〔いずもたいしゃみまさかぶんいん〕 岡山県津山市田町87
出雲大社美作分院 播磨~美作~伯耆~出雲を横断する出雲街道
〔246〕 中山神社
〔なかやまじんじゃ〕 岡山県津山市一宮695
中山神社 もともとはニギハヤヒの子孫が奉祭した神社?
〔247〕 阿智神社
〔あちじんじゃ〕 岡山県倉敷市本町12-1
阿智神社 応神朝に百済から渡来した阿智使主の一族が奉斎
〔248〕 大野見宿禰神社
〔おおのみすくねじんじゃ〕 鳥取市徳尾80
大野見宿禰神社 相撲の神さま野見宿禰は古墳に埴輪を立てた
〔249〕 樗谿神社
〔おうちだにじんじゃ〕 鳥取市上町87
樗谿神社 子供は石を投げ合い若者は刀槍で殺し合う遊びに朝鮮通信使もびっくり
〔250〕 高諸神社
〔たかもろじんじゃ〕 広島県福山市今津町519
高諸神社 実際の祭神は〝劉仁軌の乱〟を逃れてきた新羅国王
〔251〕 小烏神社
〔こがらすじんじゃ〕 広島県福山市鞆町後地
小烏神社 三原刀匠の先祖は〝小烏〟という官位を持つ新羅人だった?
〔252〕 沼名前神社
〔ぬなくまじんじゃ〕 広島県福山市鞆町後地1225
沼名前神社 縄文人は第1次渡来者、弥生人は第2次渡来者
〔253〕 亀山神社
〔かめやまじんじゃ〕 広島県呉市清水1-9-36
亀山神社 八幡神が豊後国姫島、安芸国栃原を経て宮原村亀山に遷座
〔254〕 多加意加美神社
〔たかおかみじんじゃ〕 広島県庄原市口和町向泉973
多加意加美神社 高オカミ=大名持(大己貴)=大蛇=大山祇
〔255〕 佐々井厳島神社
〔ささいいつくしまじんじゃ〕 広島県安芸高田市八千代町佐々井
佐々井厳島神社 沖の島を本拠とする宗像族と志賀島を本拠とする阿曇族
〔256〕 大山祇神社
〔おおやまづみじんじゃ〕 愛媛県今治市大三島町宮浦3327
大山祇神社 皇国史観に汚染された史観にうんざり
〔257〕 石城神社
〔いわきじんじゃ〕 山口県光市塩田石城2233
石城神社 神籠石は高句麗に源をもつ韓半島の山城
〔258〕 忌宮神社
〔いみのみやじんじゃ〕 山口県下関市長府宮の内町1-18
忌宮神社 アマノヒボコの子孫イトテ(五十迹手)の出迎え受けた仲哀帝
〔259〕 赤間神宮
〔あかまじんぐう〕 山口県下関市阿弥陀寺町4-1
赤間神宮 松雲大師が安徳祠の慶弔詩、以来朝鮮通信使の恒例に
〔260〕 彦島八幡宮
〔ひこしまやわたみや〕 山口県下関市彦島迫町5-12-9
彦島八幡宮 伊蘇=伊都は伊西(慶尚北道伊西面)のこと
〔261〕 熊野大社
〔くまのたいしゃ〕 島根県松江市八雲町熊野2451
熊野大社 クシミケヌ(櫛御気野)とスサノオ(素盞鳴)は同一神
〔262〕 八重垣神社
〔やえがきじんじゃ〕 島根県松江市佐草町227
八重垣神社 「八雲立つ」の歌は妻問いではなくスサノオの戦勝歌
〔263〕 忌部神社
〔いんべじんじゃ〕 島根県松江市東忌部町957
忌部神社 フトタマの子ヒワシ(天日鷲)はフツヌシ(経津主)の別名
〔264〕 玉造湯神社
〔たまつくりゆじんじゃ〕 島根県松江市玉湯町玉造522
玉造湯神社 櫛明玉はアマノヒボコの随神アマノマヒトツ(天目一箇)
〔265〕 神魂神社
〔かもすじんじゃ〕 島根県松江市大庭町563
神魂神社 神魂=熊野でその淵源は檀君神話の熊
〔266〕 売布神社
〔めふじんじゃ〕 島根県松江市和多見町81
売布神社 売布神は物部氏の祖神ニギハヤヒの後裔
〔267〕 武内神社
〔たけうちじんじゃ〕 島根県松江市八幡町303
武内神社 応神帝の子と武内宿禰の子が名前を交換
〔268〕 佐太神社
〔さだじんじゃ〕 島根県松江市鹿島町佐陀宮内73
佐太神社 出雲の加賀の潜戸で生まれた猿田彦は〝神在り〟の主宰者
〔269〕 美保神社
〔みほじんじゃ〕 島根県松江市美保関町美保関608
美保神社 鶏や卵を食べないのは忌避ではなく鶏林(新羅)を尊崇しているから
〔270〕 出雲大社
〔いずもおおやしろ〕 島根県出雲市大社町杵築東195
出雲大社 アマホヒ(天穂日)の子孫の出雲国造家が歴代の奉斎者
〔271〕 須佐神社
〔すさじんじゃ〕 島根県出雲市佐田町須佐730
須佐神社 出雲には意宇氏系と出雲氏=神戸氏系の二流
〔272〕 日御碕神社
〔ひのみさきじんじゃ〕 島根県出雲市大社町日御碕455
日御碕神社 稲佐の浜、日御碕海岸、北浦海岸に竜蛇がやってくる
〔273〕 須我神社
〔すがじんじゃ〕 島根県雲南市大東町須賀260
須我神社 スサノオの「八雲立つ」の歌は辰韓の言葉で詠まれもの
〔274〕 大飯彦命神社
〔おおいひこのみことじんじゃ〕 島根県江津市松川町太田199
大飯彦命神社 ツヌガアラシトはこの地で牛耕を教え田を拓いた
〔275〕 佐々布久神社
〔ささふくじんじゃ〕 島根県安来市広瀬町石原582
佐々布久神社 大和の都が危険で伯耆に移ったというが?
〔276〕 苗村神社
〔なむらじんじゃ〕 滋賀県蒲生郡竜王町綾戸468
苗村神社 那牟羅彦・那牟羅姫はアマノヒボコの眷属?
〔277〕 惟喬親王陵
〔これたかしんのうりょう〕 滋賀県東近江市永源寺町君ヶ畑
惟喬親王陵 皇位を継げず深山幽谷を流浪した惟喬親王
〔278〕 福泊神社
〔ふくどまりじんじゃ〕 兵庫県姫路市的形町福泊402
福泊神社 韓泊→唐泊、韓津→唐津、韓国神社→辛国神社などは〝韓かくし〟
〔279〕 国魂神社
〔くにたまじんじゃ〕 三重県津市西古河町23-26
国魂神社 高句麗系種族が大和を平定、国魂神も結局は渡来神
〔280〕 月読神社
〔つきよみじんじゃ〕 京都府京田辺市大住池平31
月読神社 大嘗祭で天皇が座るのは隼人の編んだ籠
あとがき
まえがき
写真紀行『鳥居のある風景』シリーズ第7弾は、〝岡山・広島・山口・島根〟です。補遺として書き漏らした所を若干加えました。
崇神朝に、四道将軍の一人として、吉備津彦が西海に派遣されました。はたしてそうでしょうか。『日本書紀〈雄略紀〉』における吉備下道臣前津屋の誅殺譚や吉備上道臣田狭の排除譚などを見ますと、その時期、雄略帝(大和政権)に対抗しうる一大勢力が吉備にあったことがわかります。であれば、吉備津彦は、派遣されたのではなく、その地域の国主(王)であったのではないでしょうか。
吉備津彦は、第7代孝霊帝の第3王子とされ、五十狭芹彦(=吉備津彦)という名で、吉備津彦=五十狭芹彦=笥飯(気比)大神=去来紗(伊奢沙)別=天日槍という関係になり、アマノヒボコと同人(神)格です。くわしくはハンデウン著「アマノヒボコ(天日槍)王朝」(Kindle版1~8巻)をご一読ください。ということは、大和朝廷以前に、アマノヒボコ王朝があったことの証左といえましょう。
「古墳文化という新しい文化の展開と軌を一にする崇神王朝の成立、初期ヤマト国家の成立を、朝鮮半島からの新たな文化的刺戟をぬきにしては考えられないとすれば、イリ王朝の成立は明白に渡来系種族による覇権掌握を示唆する」などと考証されていますように、大和朝廷の成立は、紀元660年に神武帝が即位したという遠い過去のことではありません。神武東征は虚構譚といわれています。大和朝廷以前の吉備津彦(=アマノヒボコ)の頃は、アマノヒボコ王朝が吉備、若狭、丹後、但馬などに存在していたのです。
『日本書紀』は、〝言葉明瞭、意味不明〟の